薬剤師のためのおすすめの転職サイト
\20代30代に強い薬剤師転職サイトNo.1/
登録無料
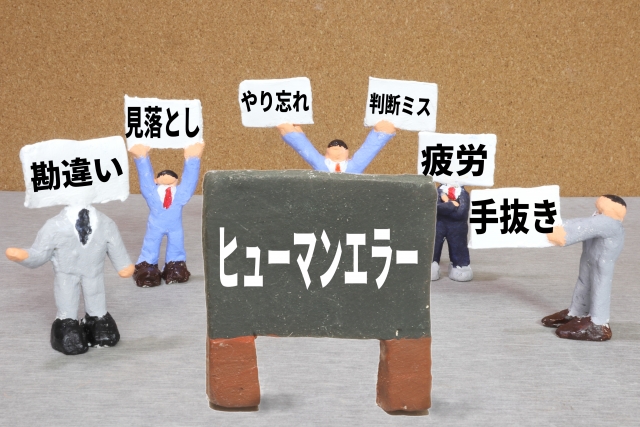
薬剤師として働く中で避けて通れないのが「ヒヤリハット事例」です。
これは実際に患者に被害が及ぶ前に気づけた誤りやインシデントのことで、医療事故を防ぐための重要な学びの材料になります。
処方箋の読み間違い、類似薬の取り違え、投薬時の確認不足など、現場では数多くのヒヤリハットが存在します。
本記事では薬剤師に多いヒヤリハット事例を具体的に紹介しながら、どのように防止していくべきかを解説していきます。
日々の業務で同じ過ちを繰り返さないために、事例を知っておくことは大きな意味を持ちます。
新人薬剤師はもちろん、経験豊富な薬剤師にとっても再確認のきっかけとなるはずです。

薬剤師が日々の業務を行うなかで、最も注意しなければならないのは「患者の安全を守ること」です。
そのために欠かせないのが「ヒヤリハット事例」の振り返りです。ヒヤリハットとは、重大な事故には至らなかったものの、「ヒヤッとした」「ハッとした」ようなインシデントを指します。
つまり、実際に誤薬や投与ミスなどが患者に影響する前に気づけた出来事です。
一見すると単なる小さなミスのように見えるかもしれませんが、これらを記録・共有し、原因を分析することで、将来の医療事故を未然に防ぐことができます。
薬剤師は処方監査や調剤、服薬指導といった多くの場面でヒヤリハットに遭遇しやすく、再発防止のために組織的に活用していくことが極めて重要です。

薬剤師のヒヤリハットは多岐にわたりますが、大きく分類すると「処方監査」「調剤」「投薬・服薬指導」「薬歴管理」などの場面で発生します。
医療現場は多職種が関わり、患者一人に対して複数の処方や情報が絡み合うため、ちょっとした確認不足が大きなリスクにつながります。
たとえば、処方箋の読み間違いや薬剤名の類似による取り違え、調剤時の分量ミス、患者への説明不足などが典型例です。
さらに、近年はジェネリック医薬品の種類が増えたことで、同じ成分でも異なる名称の薬が多く存在し、ヒヤリハットを誘発しやすい状況もあります。
薬剤師が遭遇する典型的な事例を理解しておくことで、自身の業務に活かせる学びが得られるでしょう。
処方箋を受け取った際に、医師の筆跡が読みづらかったり、似たような薬剤名を誤って認識したりするケースは少なくありません。たとえば「ノルバスク」と「ノルバデックス」のように薬剤名が類似している場合、処方箋を見間違えて調剤を進めそうになる事例があります。また、処方量や投与日数の記載を見落とすこともあり、実際にはあり得ない大量投与が入力されてしまうこともあります。こうした場合、多くは疑義照会で防止されますが、監査の段階でしっかり気づくことが不可欠です。読み間違いのリスクは新人薬剤師に限らず、ベテランでも業務が忙しい時に起こりやすいため注意が必要です。
調剤室で多いヒヤリハットが、類似薬の取り違えです。たとえば、錠剤の大きさや色が似ている薬剤を取り違えるケースや、同じ薬効分類に属する薬剤を間違えてピッキングしてしまうケースがあります。代表的な例として、睡眠薬の「デパス」と胃薬の「デパケン」など、名前が似ている薬の混同です。さらに、ジェネリック医薬品が複数存在する場合、棚の配置や包装の違いによって誤って別製品を取り出してしまうこともあります。これらは調剤監査の段階で発見できれば大事に至りませんが、二重チェックやピッキング時の指差し確認が欠かせません。
患者に薬を渡す段階でもヒヤリハットは多発します。たとえば、同じ名字の患者が続いた場合に、薬袋を取り違えて渡しそうになった事例があります。また、服薬指導の際に飲み方を正しく伝え忘れたり、説明内容を誤ったりするケースもあります。特に抗生物質やワーファリンなど服薬方法や注意点が重要な薬では、説明不足が重大なリスクに直結します。患者の理解度を確認せずに説明を終えてしまうこともヒヤリハットの一因です。そのため、投薬時には必ず患者の名前をフルネームで確認し、説明した内容を復唱してもらうなどの工夫が必要です。
調剤報酬や電子薬歴の入力時に、分量や日数を誤って入力してしまうケースも代表的なヒヤリハットです。たとえば「1日3回 1錠」と入力すべきところを「3錠」と誤入力すると、処方量が3倍に膨れ上がってしまいます。また、投与日数を「7日」と入力すべきところを「70日」としてしまうケースもあります。これらは監査や最終確認の段階で気づければ問題になりませんが、入力作業は単純作業に見えて集中力を要する部分であり、ダブルチェックが必須です。
薬剤師の重要な役割の一つに、薬歴管理と相互作用の確認があります。しかし、忙しい業務の中で確認が不十分となり、ヒヤリハットが生じるケースがあります。たとえば、高齢患者が複数の医療機関から処方を受けている場合、同じ成分の薬が重複してしまうことがあります。また、併用禁忌薬の確認を見落としてしまい、処方の矛盾に気づけないこともあります。電子薬歴のアラート機能があるとはいえ、すべてをシステムに依存するのは危険であり、最終的には薬剤師自身の確認力が求められます。
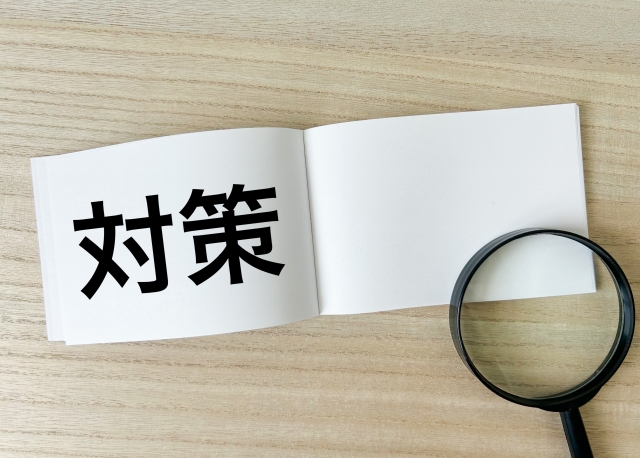
ヒヤリハットを防止するには、個人の注意力だけに頼るのではなく、システム的な工夫やチームでの取り組みが不可欠です。
まず、調剤時には「指差し呼称」を徹底することで、無意識に起こる取り違えを減らせます。
また、投薬時には必ず患者の名前をフルネームで確認し、同姓患者との取り違えを避けることが重要です。
さらに、電子薬歴や処方監査システムのアラートを過信せず、薬剤師自身の知識を活かしてダブルチェックを行う姿勢が求められます。
現場で共有されるヒヤリハット事例は、他の薬剤師にとっても学びとなるため、積極的にカンファレンスや勉強会で紹介し、再発防止につなげていくことが効果的です。

薬剤師の業務は患者の命に直結する責任重大な仕事であり、些細なミスが重大事故につながる可能性を常にはらんでいます。
そのため「ヒヤリハット」を軽視せず、日常業務で気づいた小さな事例を共有・分析することがとても重要です。
処方監査、調剤、投薬、薬歴管理のどの場面でもヒヤリハットは発生しますが、それを未然に防ぐ工夫は数多く存在します。
指差し呼称、ダブルチェック、患者確認の徹底、薬歴や相互作用の慎重な確認など、日々の実践が未来の安全につながります。
薬剤師一人ひとりが事例から学びを得て、組織全体で取り組むことで、より安全で信頼される医療の提供が実現できるでしょう。